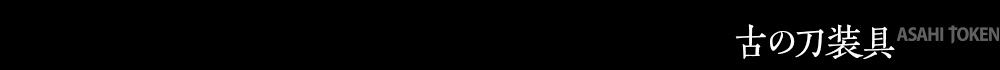TOSOGU OPINION SITE
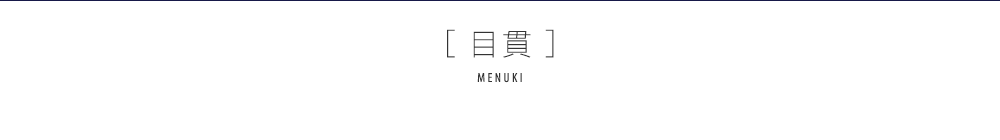
目貫
藻に桶図(無銘・古金工)
商品番号 :MK-039-SS
桃山期 保存刀装具 桐箱入
150,000円
山銅地 容彫 金袋着
表/長さ:3.98 cm 幅:1.51 cm 高さ:0.54 cm
裏/長さ:3.89 cm 幅:1.57 cm 高さ:0.53 cm
小道具における画題の表現は場合によってとても奇異にみえるものです。松葉もそうですが、この藻もそんなうちの一つ。細い枝先をどう表現するか、金工たちの創意工夫が見る者へ伝えるイメージに納得してしまいます。小道具の画題などに興味のない人にとっては、紐がひらひらしているようにしか見えませんが「これは藻です」と一旦刷り込まれれば勝手に頭が風景を描き出し、その世界に引き込まれてしまう・・・それが優れた金工の力量なのかもしれません。本作の画題は藻に桶。桶は金の袋着で色付けされており、周りの2種類の藻にうずくまる様は、作者が意図したのか解りませんが桶ではなくまるで花のような錯覚を覚えます。裏行を見ると数カ所に圧出を調整した叩き跡が残っています。ちょっとした凹みにも気を遣う金工のこだわりが伝わってきます。
ところで本作の地金は山銅であると鑑定書に書かれています。う〜ん、お日様の下で見ても蛍光灯の下で見ても黒いよなぁ・・・私の眼は節穴で信用出来ませんが、赤銅に見えるのは錯覚なのかな。確かに赤みがかっているけど、これより赤っぽい小道具には赤銅と書かれているのもたくさんあって、どこがどう違うのでしょう。色揚で表れる現象? 色の違い? 重さの違い? 金工や派閥・一門? 地金を削って調べている(これはないと思います)? イメージ・・・まさか、主観?