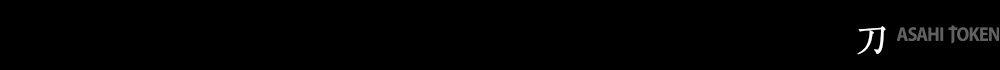TOKEN OPINION SITE

刀
下総大掾藤原兼正 越前住
商品番号 :B-045-I-136
江戸前期 越前 保存刀剣 白鞘・拵付
480,000円
刃長:63.7 cm 反り:1.7 cm 重ね:0.70 cm
- 体配
- 本造、庵棟、中心は生で孔は一つ、鑢目は筋違。
- 地肌
- 板目肌流れ心に柾がかかり、地景が出る。棟寄りは柾目肌。
- 刃文
- 焼幅広く、小沸出来の大五の目乱に箱乱を交互に連続し、表裏ほぼ揃いに焼く。箱乱の匂口に沿って小沸がつき、砂流風の所作が出て、短い足がよく働く。
- 鋩子
- 直ぐに小丸、浅く返る。
- 備考
- 京焼出風に始まり、高低差のないゆったりした五の目が数個と箱乱がセットになった刃文が連続して続く本刀。表裏揃って焼き上げていることから誰かの写だと思われます。越前という国も考えれば、隣国の兼若あたりの影響を受けたのでしょうか。その匂口も小沸出来の深く柔らか。越前関によくあるとされる厳つい刃もなく、丸味を帯びた刃縁は冴えています。良い出来だと思います。鍛のせいでしょう、地肌は少し荒れ気味でですが、肌立っている訳ではありません。そして地景がよく現われています。
姿は寛文・延宝頃の反りが浅く元先に差がある中切先。ある意味、無骨さはありませんが、北陸ものらしい姿をしています。作刀した兼正は濃州関兼法五代孫とされていますが、それ以外に越前諸工との関連を示す資料がものが少なく未詳な刀工。下総大掾を受領し、江戸や彦根でも打ったという作例もあるぐらいですから、結構出張って活躍していた刀工なのかも知れません。
本刀には幕末期はある拵がついています。柄前には赤銅地・金色絵の波に龍の縁頭、目貫は故事を画題にした人物(よく見えないので推測)で多分素銅に色絵、鮫皮も当時のママのようです。鞘は乾黒石目地では少し痛みがありますが、これも古そうです。中身の刀もそうですがそれほど派手ではなく、どちらかといえば質素な身鞘といった本刀。これが当時の普通の武士の備えだったのでしょうね。