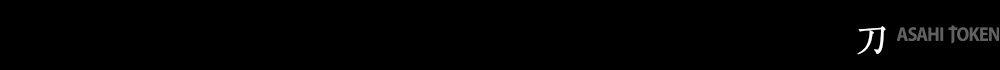TOKEN OPINION SITE

刀
濃州関住兼先作 置
商品番号 : B-SD393
戦国時代 美濃国関(岐阜) 特別保存刀剣 白鞘入
1,815,000円
刃長:71.0cm・2尺3寸4分半 反:1.3cm・4分3厘
元幅:32.0mm 先幅:24.0mm 元重:7.5mm 先重:5.0mm 目釘孔:1
- 造込
- 本造で行の棟。鎬やや高く鎬幅は広め。
- 体配
- 反深く、さほど先細らず中切先がよく延びる。
- 地肌
- 総体に良く詰んだ均一な板目肌で柔味があり、所々に大きめの板目が交じる。刃肌は良く詰み、鎬地は柾目が強く棟寄りは特に強い。焼出移が立ち、鎬筋近辺は移っ気が強い。
- 刃文
- 匂口締まり心で柔味があり、沸がよく付く乱刃。尖,矢筈,五の目丁子などが入り交り、刃中は足入りが主体となる。総体に刃幅が広く表裏の出入りが揃う。
- 鋩子
- 本刃同様に乱込み、先は深めで返は寄り、滝落状に深く返る。刀身の中程下辺りまで棟焼が現れる。
- 中心
- 平肉豊かに付き、やや刃上りの栗尻で棟に肉が付く。独特の鑢を鷹の羽にかけ、指表には居住地を添えた刀工銘、指裏には『置』と刻る。

戦国時代に製作された濃州関住兼先の刀です。
差表には居住地を独特の崩字を用いて刀工銘と共に刻り、差裏には「置」と読める銘が刻ってあります。中心仕立を見ると「置」の下部には銘が刻ってあったと思われます。「置」という銘から、奉納刀や献上刀であった可能性も考えられます。詰んだ地鉄や柔みのある匂口と中心仕立から、良質な鋼を用いて入念に作刀された事が窺えます。実戦で存分に使われた為か末関物の刀の現存品は存外少なく、本刀がこの様な状態で残されているのは裏銘の「置」が大いに関係しているのかもしれません。江戸時代以降の刀剣に大きな影響を与えたのに謎が多い関の刀工ですが、本刀の存在は関刀工の研究を進めるための大きなヒントが隠されているかもしれません。ロマンのたっぷり詰まった魅力的な一振です。