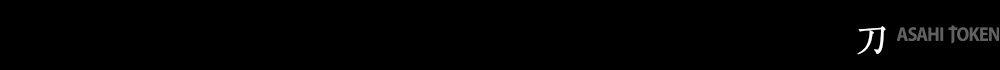TOKEN OPINION SITE

脇差
摂津住康永
商品番号 : C-SD415
江戸時代前期 摂津(大阪) 特別保存刀剣 白鞘入
308,000円
刃長:47.7cm・1尺5寸7分5厘 反:9.0cm・3分
元幅:28.5mm 先幅:20.0mm 元重:6.5mm 先重:4.5mm 目釘孔:1
- 造込
- 本造、鎬は低めで行の棟。
- 体配
- 反は浅めで先細り中切先。
- 地肌
- 小板目肌でとてもよく詰む。刃肌よく詰み刃中の刃縁近くに所々流れた肌が現れる。鎬地棟寄りは柾目が交じる。
- 刃文
- 焼元から2寸5分程は大人しく大阪風に焼き出し、それより上部は匂口深く焼幅の広い濤瀾風の大乱となる。五の目が2~3で一団となった五の目が主体でやや角張る気味があり、刃文の表裏がピタリと揃う。太い足が長めに入り帯状となり、足には砂流が掛かる。
- 鋩子
- 直調で先は小丸で深め。先寄って返は小鎬先の辺りまで浅めに返る。
- 中心
- 平肉付き、棟方刃方にも丁寧な肉が付けられる。研溜は化粧鑢が置かれて尻は入山形。鎬筋を中心に大振りの銘が堂々と刻られる。

紀州石堂と呼ばれる新刀備前伝を代表する石堂一派の刀工である、河内守康永の脇差です。
本脇差はとてもよく詰んだ地鉄に焼幅の広い濤瀾刃を見事に焼いています。康永の上手さが十分に分かる出来で、さすがは高い技術を必要とする丁子刃を得意にする石堂一派と言えます。中心の化粧鑢も丁寧で、手に吸い付くような見事な肉置となっています。濤瀾刃で有名な助広や越後守包貞にも引けを取らない、康永の上手さと丁寧さを存分に味わえる一振です。