INTELLIGENCE
♮ 一振の追憶 その11(無銘・兼光)
Copywritting by Nobuo Nakahara
- 刀
- 無銘(兼光)
刃長/二尺四寸弱、反/六分、本造、行の棟、中心は磨上、孔は二つ。 - [地肌]
- 小板目肌に杢目風の板目肌が交じり、少し肌立ち心。乱移が鮮明にあらわれている。
- [刃文]
- 匂出来、下の方は五の目乱、片落五の目乱となり、上の方は小五の目乱が数個づつ一団となって一つの大きな乱となり、ややコズんだ乱を間に交えたもので、表裏が揃う。
- [鋩子]
- 乱込、先は小丸で返は少し。
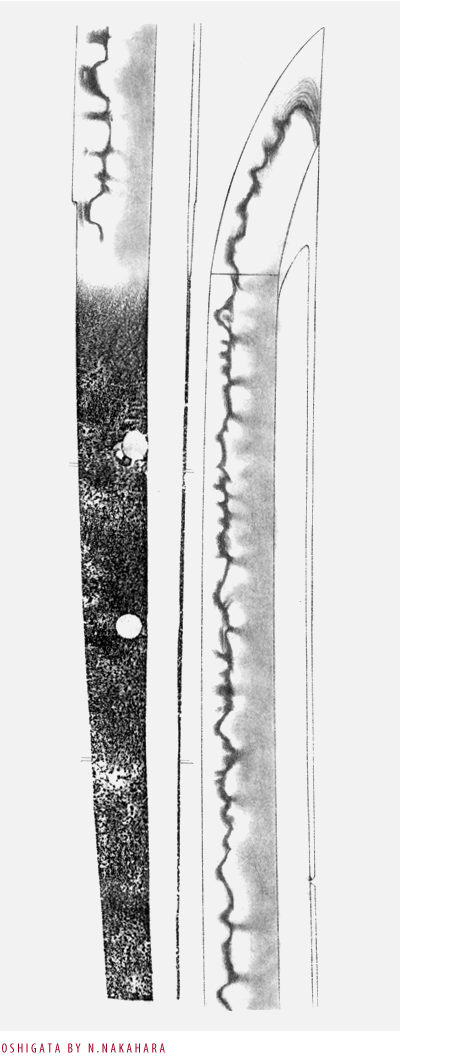
本刀は無銘ですが、その刃文の形と乱移が鮮明にあらわれている地肌、そして大切先の姿から兼光と極められたものです。
さて、私は無銘を排斥する事が多いのですが、拙著『刀の鑑賞』にも述べた様に、全ての無銘を排斥する事はありません。では、どのような無銘は排斥しないのか、という前に、どの様な無銘を嫌うのか。それは時代が古い一流刀工に極められていながら磨上っていない無銘を嫌うのであり、?を提示するだけのことです。
一流刀工なら磨上ても銘は絶対に必ず残します。これはごく基本的な常識であり、紛れもない真実であると同時に理屈でもあるのです。まして、磨上っていないか、必ず銘が残される程度の長さの磨上での無銘は不合理極まりないものです。このようなケースに一流刀工(有名刀工も含む)の無銘極を発生させる余地がでてくるのです。因みに、本刀には二つの目釘孔がありますが、この二つの目釘孔の中程あたりまで刃文(匂口)の形が残されていますし、刃区下の乱移の角度と形状から見て、約二寸五分弱程の磨上は確実に施されています。
しかしです。では本刀は元来から無銘であったのを磨上たのかという事になりますが、私はそうではないと思います。つまり、いつの時か無銘にされてしまい、本来の銘よりも上位の極を望んでの無銘化でしょう。しかし、本刀は確かに磨上られているのです。これは一番の救いでしょう。ただし、本刀には延宝二年の折紙(本阿弥光常)が附帯していて、磨上の兼光と極められていますし、古い大名鞘に収まっているにしても、私は兼光ではないと思っています。
かつて、本刀を研究会で解説した時、所持者の方がその場に出席されていましたが、それを参会者に知らせた上で私は「兼光ではないと思います」と失礼ながら説明しました。その折、所持者の方は「気にしないで、本当に感じた事を言って頂いたと思っています。怒ってはいません。」と微笑ながら私に返答されたのを今でも覚えています。その上、その研究会の主催者の方が私の説明と所持者の方との応答を隣で聞いておられましたが、その方が目を丸くして呆気にとられた様に言葉をなくしてビックリされている光景も今だに忘れられません。別に手柄話をするつもりはありませんが、私にも相当勇気がいる説明であった事は事実ですが、それにも増して、私なりの無銘極の本論と本質を話したかったのです。
世上、一流刀工の偽銘を刻る輩と、それに加担し利を貪る連中がいますが、それに逆行して一流刀工銘を消し去るでしょうか。そんな事をしたら偽銘を刻る連中は怒りますよ・・・。
昔の本阿弥家の無銘極は「一段ランクを上げて極めるのが礼儀である」とされてきましたが、これ自体が無銘極の正体を自ら告白しています。「一段ランクを上げる」というのは、元はランクが下というのを自ら認めたものです。つまり、無銘にしてしまった元凶(犯人・細工人)でなければ知り得ない秘密であり、自ら手をくだしていない無銘化のケースにも、暗黙というか阿吽の呼吸の如きものでの極です、
何故にこの様な行為をするのでしょうか、それは利益を生むからでしょうし、所持者も喜ぶという真実でもあります。こうしたケースでの最悪のケースは、大磨上風をよそおった生中心への極でしょう。このケースだけは絶対に排斥して然るべきです。
それにしても本刀は“いい刀”ですし、おそらく兼光周辺の刀工の作とみるべきでしょう。いづれにしても良い刀です。それを私は絶対に否定しません。つまり、磨上っているのが確実で、移が歴然とある作は国(生産地)がある程度限定が出来るので、無銘でも排斥はしません。しかし、備前の一流へは極められない事は前述の通りです。
(平成二十八年三月十日 文責・中原信夫)


