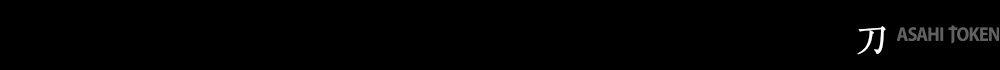TOKEN OPINION SITE

刀
備前國住長舩五郎左衛門尉清光作之 岡部豊後守住代也 天文二十一年八月吉日
商品番号 : A-SD406
戦国時代 備前(岡山県) 重要刀剣(「所持銘のある末古刀」p.73所載) 白鞘入・拵付
お問合せください
刃長:68.4cm・2尺2寸5分半 反:19.0cm・6分半
元幅:32.0mm・1寸5厘 先幅:22.0mm・7分2厘 元重:9.0mm・3分弱 先重:6.0mm・2分弱 目釘孔:1
- 造込
- 本造、鎬高く鎬幅広めの利刀姿。立上りのあるやや低めの行の棟。
- 体配
- 反深めでやや先細り、中切先延び心の体配。
- 地肌
- よく詰んだ小板目に板目交り。板目が鎬地を超えて現れ、鎬地と刃縁近辺に流れ心が現れる。刃肌よく詰み精美。深く焼き込んだ焼元から移が立ち、鎬筋辺りに移っ気がある。
- 刃文
- 焼幅広めの直刃調。匂口締まり心の小沸出来で、総体に刃縁よく締まって冴える。直刃の中に小互の目や喰違刃が交じり、刃中は足と匂崩が点々と現れ、”清光のよだれ”と呼ばれる特徴的な所作が現れる。
- 鋩子
- 本刃同様の直調で、表は一枚に近く裏も深い。返は共に寄って深い。物打辺りに棟焼があり、表の横手下鎬筋上に飛焼がある。
- 中心
- 肉置とても豊かで、刀工銘と年紀だけでなく注文銘まで流暢に速い鏨で刻る。鑢は浅い勝手下。やや刃上りの栗尻で棟刃共に肉は角。

戦国時代備前長舩の代表刀工の一人である、五郎左衛門尉清光(ごろうざえもんのじょうきよみつ)の作です。
革新的な刀工が多く出た末備前で古調な直刃の名人として知られ、毛利元就が厳島合戦の際に陣太刀を打たせたりと、活躍中から大人気の刀工です。様々な板目の交った古調な肌に自然みのある変化が現れた刃文を焼いた、「これぞ五郎左衛門」という本領が発揮された一振です。五郎左衛門の特徴がよく現れた作ですが、利刀造の体配や殊に深い鋩子や広めの焼幅など、戦国時代の最新の要望にも応えた意欲的な作でもあります。清光自身としても余程の自信作だったのか中心仕立も抜かりが無くとても丁寧で、自信満々の堂々とした銘を刻っています。刀身のみならず中心まで健全度の非常に高い一振です。