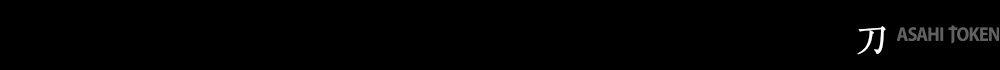TOKEN OPINION SITE

刀
笠間一貫斉繁継作 昭和十一年八月日 八幡大菩薩
商品番号 :B-053-120
現代 白鞘
450,000円
刃長:66.7 cm 反り:1.50 cm 重ね:0.72 cm
- 体配
- 本造、庵棟、中心は生で孔一つ。鑢目は化粧に勝手下がり。
- 地肌
- 小板目肌よくつんで流れ心に無地風の肌となる。鎬地棟寄りは柾目肌。
- 刃文
- 直調の細かい五の目乱に逆丁子風の小足が盛んに所作する。匂口は締り心の匂出来、移が現われる。
- 鋩子
- 直に入り、表は掃掛て、裏は弯れて掃きかける。返は尋常。
- 備考
- 締り心の匂口が小五の目となるあたりは、新々刀期の備前ものを見ているようです。そこから逆丁子風の小足が盛んに出て、中々賑やかです。そういうわけで、備前の写をやったのは明白で刃文の出来は上手くまとまっています。移もうっすらと出て、華を添えているようにも思えますが、ちょっと気になるのは地肌。小板目が詰まれて無地風になるのは評価できます。ただ、ごく小さな鍛え疵が所々に見られます。これは戦争直前の時代を考えると、材料不足も含めて如何仕方ないのかもしれません。しかし、本刀は大量生産の軍刀の類いではありません。
ちょっと変った点は、腰刃風の所作が見られることでしょうか。指表の焼出部分は広く盛上がっています。指裏は鎬地にかかるように飛焼風の所作が2カ所確認できます。これを腰刃とよんでよいのか自信はありませんが、意図した所作には違いありません。表の腰刃なんかは富士山のようにも見えます。とすれば、裏側の飛焼は富士にかかる雲・・・妄想にも程がありますね、ちょっと飛躍し過ぎです。総体には上出来とはいえませんが、昭和初期という作刀時代を色濃く伝える一振だと思います。