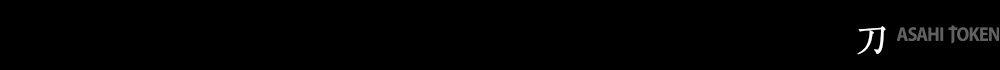TOKEN OPINION SITE

刀
山城国粟田口藤原忠縄 於播州作之
商品番号 : B-SD346
江戸時代前期 山城・播磨(京都・兵庫) 特別保存刀剣 白鞘入・拵付
¥1,001,000
刃長:66.4cm・2尺1寸9分 反:1.5cm・4分9厘
元幅:30.5mm 先幅:19.0mm 元重:8.0mm 先重:5.0mm 目釘孔:1
- 造込
- 本造、立上のたっぷり残った低い行の棟。
- 体配
- 反やや深めで先細り中切先がやや延びる。
- 地肌
- 小板目肌とてもよく詰み地景交じる。棟寄りに流れた柾目が少し現れる。
- 刃文
- 匂い口やや深めで小沸のよく付いた乱刃。大人しく焼き出し、連なった丁子と弯を繰り返す。物打辺りは丁子になって鎬に近く、表裏の出入がピタリと揃い、足入り多く足に砂流が掛かって帯状も現れる。
- 鋩子
- 直調で帯状となり、小丸で深く返りも深い。指裏に棟焼がポツポツと現れ、総体に棟を軽く焼く気味がある。
- 中心
- 丁寧な平肉が付き、長銘に独特の書体で刻る。鑢は筋違、棟は角。

初代忠綱の初期銘である忠縄の刀です。
生国は播州姫路、山城に移住後に大阪へ移るといいます。表銘に山城国とある事から本刀は山城移住後に生国の播磨へ赴いて打った刀であり、ごく丁寧に仕立てた中心と銘に忠綱の並々ならぬ意気込みが現れています。精巧な地肌に大胆な刃文を見事に焼いており、初代忠綱壮年期の代表作といえる一振です。息子の一竿子忠綱に注目が集まりがちですが、本刀には「親忠綱あってこその一竿子である」と考え直させられます。
大坂新刀の礎を築いた忠綱の名作をぜひ末長く御愛蔵して下さい。