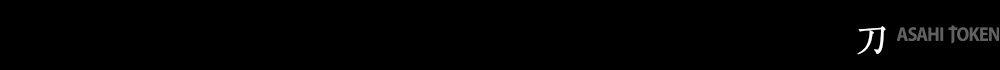TOKEN OPINION SITE

刀
雲州住冬(以下切)〈雲州冬広〉
商品番号 : B-SD391
新古境 出雲(島根) 保存刀剣 白鞘入・拵付
売約済
刃長:64.8cm・2尺1寸4分 反:1.1cm・4分弱
元幅:30.0mm 先幅:21.5mm 元重:6.5mm 先重:5.0mm 目釘孔:3
- 造込
- 本造、高めの行の棟。鎬幅広く鎬低め。
- 体配
- 反浅めで先細らず、切先延びる。
- 地肌
- 板目鍛に流れ肌交じり。底によく詰んだ小板目が沈む。刃肌よく詰み、鎬地棟寄は流れる気が強い。樋底の肌よく詰み、全体に移っ気がある。
- 刃文
- 匂口の締まった小沸出来の広直刃調。中程より上は足入り匂崩多く、箱風や角張り心の乱が交じる。総体に二重刃,喰違刃など縦の所作が多く、やや弯れ心で出入があり沸がよく付く。
- 鋩子
- 直調で表は喰違刃、裏は沸匂凝った小足よく入り地に二重刃が掛かる。先小丸でやや上りやや寄り心。
- 中心
- 樋を避けて刻銘される。二度の磨上が行われていて、棟は角で尻は切。
- 彫刻
- 生樋と思われる掻通樋で樋先下がる。銘を尊重した磨上が行われ、指裏は中心の内で掻流になる。

戦国時代末期から江戸時代最初期の製作と思われる雲州冬広の刀です。
冬広は戦国時代に相模から若狭へ移住したとされ、若狭定住後も備前や伯耆などへ出張駐鎚した人気刀工です。出雲は良質な砂鉄の産地として有名であり、本刀は冬広が良鉄を求めて出雲に移住した後の作と思われます。丈夫さと斬れ味を評してか二度の磨上が行われていて、元来は刃長が2尺5寸程ととても長寸でした。それ程の長寸でありながら匂口にムラのない上出来で、地鉄もよく詰んで良質であり、通常は行われない生の掻通樋で製作されています。この事からも、製作において地鉄の選定から鍛錬はもちろん、造込から焼入に至るまで拘り抜いて行われた事が伺えます。まだまだ世相の安定しない時代により良い刀剣を造ると冬広が強い意欲を持っていた事が伝わってくる一振です。