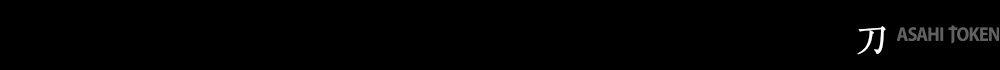TOKEN OPINION SITE

脇差
応岡本稚義需 竜渕子安一作 文化七庚午二月吉日
商品番号 : C-SD387
江戸時代後期 薩摩(鹿児島) 特別保存刀剣 白鞘入
385,000円
刃長:50.4cm・1尺6寸8分 反:9.0cm・3分
元幅:30.5mm 先幅:21.0mm 元重:8.0mm 先重:5.5mm 目釘孔:1
- 造込
- 本造、低めの行の棟で立上りがしっかりと残る。鎬幅広めで鎬低い。
- 体配
- 反やや深めで先細り中切先。
- 地肌
- 詰んだ板目鍛。刃文の肩から腰に掛けて流れた柾目肌が見られる。刃肌平地以上によく詰み、刃区から棟区に向けて焼出移が立つ。
- 刃文
- 小沸出来のフックラとした匂口で、下から7寸程で富士見西行、それより上はよく揃った丁子乱となる。足入り多く太く帯状となり、足には細かい砂流が掛かる。
- 鋩子
- 直状で切先の刃幅広く、先は小丸~中丸でやや上がる。返は寄って虎の尾状で深い。物打辺りまで棟焼が見られる。
- 中心
- 均一にピンと張った肉置で、棟は肉で刃上り栗尻。平面と棟に香包鑢があり、棟方は踏張が付く。指表に注文銘と刀工銘、指裏に年紀を刻る。

江戸時代後期の文化7年(1810年)に薩摩で製作された、竜渕子安一の注文打です。
刀身だけでなく中心の肉置や鑢掛けまで丹念に仕上げられた本刀ですが、実は謎だらけの一振です。銘に「安」を使っていることや中心の姿からは薩摩波平一派との関係を強く感じ取れますが、刃文は波平一派が家伝とした直刃ではなく富士見西行に揃った丁子刃を焼いていますし、鑢は大坂の越前守助広に影響が見られる丁寧な香包の化粧鑢が棟にまで施されています。揃った丁子となれば横山祐定系,三品,浜部などの上手が全国にいますし、特殊な化粧鑢となれば手柄山,水心子一門,尾崎系などがそれぞれ独自の手法で行なっていますが、本刀にピタリとは当てはまりません。さらに鎌倉時代から続く名門島津家の刀工となれば、日本各地の名工達と複数関わりがあっても不思議ではありません。ならばなぜここまで上手な刀工の現存が極めて稀なのか。見れば見る程に惹き込まれてしまう一振です。