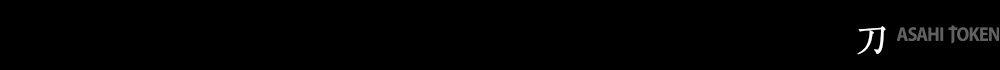TOKEN OPINION SITE

脇差
河内守国助
商品番号 : C-SD399
江戸時代初期 摂津(大阪) 特別保存刀剣 白鞘入
売約済
刃長:56.6cm・1尺8寸7分 反:5.0cm・2分弱
元幅:34.0mm 先幅:31.0mm 元重:7.5mm 先重:6.5mm 目釘孔:2
- 造込
- 本造、行の棟。鎬幅広く鎬高い。元来は長巻として制作されたと思われる造込。
- 体配
- 反ごく浅く身幅先細らず大切先。
- 地肌
- 小板目肌よく詰み板目交じり。鎬地も同様で棟寄りは柾目が強い。刃肌刃寄がよく詰む。
- 刃文
- 小沸出来で匂口のフックラとした大出来。大坂風に焼出し、上部に従い焼幅広くなる。表裏の出入は揃うがピタリとは揃わず、やや太めの丁子足よく入り、足に細かな砂流が掛かる。
- 鋩子
- 横手下から7分程は本刃同様、それより上は大人しくなり、大きく二つ弯れて先小丸。切先の刃幅は本刀中最も広く、返は滝落し状で浅め。
- 中心
- 平肉付き、棟は角で尻は切。元来は今よりも長かったと推測される。鑢は独特で筋違。佩表鎬地に独特の崩した銘を刻る。

大坂新刀の礎を築いた、初代河内守国助の脇差です。
銘や中心や刃文の形式から、元来長巻だったものを脇差に仕立て直した一振です。仕立て直しの手間やリスクを考えれば、脇差をもう一振注文した方が経済的だったと思いますが、この刀の斬れ味や初代国助の高い技量を評価しての仕立て直しと思われます。堀川国広へ入門以前から初代国助は作刀出来たとされ、普段は石堂一派を感じさせるような丁子刃が特徴とされます。しかし、本刀は弯主体で砂流掛かり沸が強い堀川一派の特徴がよく現れた作風です。中心にもこの刀を少しでも健全に残そうと苦慮した点がよく現れています。この刀を脇差に仕立て直した人の熱い思いも感じながらぜひ大事にして頂きたい一振です。